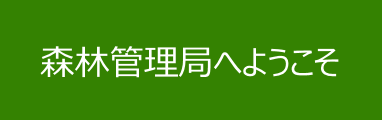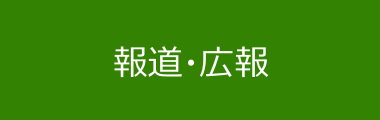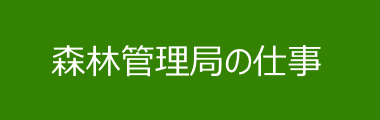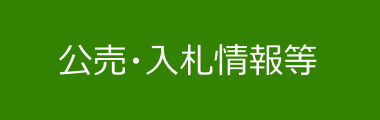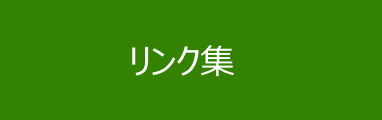研究のもり
仕事のなかから生まれるアイディア、研究のページです!
岩手北部森林管理署では、職員の業務に対する疑問や探求心を大事に考えています。
ひとり、ひとりの?を「どうして、なぜ」から「こうしたら、こうなった」「こうすれば、こうなるのでは!?」と考え工夫しながら新たな技術の開発や業務に役立つ改善、ソフトの開発に取組んでいます。
|
|
|
|
|
民国連携よるコンテナ苗の発表 |
天然更新を活用した試験 |
特別賞田山小学校 |
公開論文一覧
|
|
年度 |
研究名 |
氏名 |
受賞 |
|
1 |
平成19年 |
カラマツ天然更新に関する一考察 | 技術専門官 松尾 亨 |
平成20年度 最優秀受賞 |
|
2 |
平成19年 |
在来植物による緑化技術の開発 | 岩手北部森林管理署 工藤 庸子 技術専門官 松尾 亨 東野建設工業株式会社 羽柴 徳男 |
|
|
3 |
平成21年 |
特別発表 地域にとって有って |
岩手北部森林管理署長 春原 武志 | |
|
4 |
平成21年 |
発見!森林の秘密 | 田山小学校5年生8名 |
平成21年度 特別賞 |
|
5 |
平成21年 |
上外川学習教育林の整備について |
浄法寺森林官 田口 暁史 新町森林官 木村 雄大 |
平成21年度 優秀賞 |
|
6 |
平成22年 |
「国有林って何ですか?」に応える、 |
販売係長 佐藤 次郎 |
平成22年度 会長賞 |
|
7 |
平成22年 |
妖精の住む森を利用した |
浄法寺森林官 田口 暁史 新町森林官 木村 雄大 |
平成22年度 最優秀賞 |
|
8 |
平成23年 |
天然更新を活用した牧草の森林化について | 技術専門官 松尾 亨 | 平成24年度 東北森林管理局 技術発表会 森林技術部門 優秀賞 |
|
9 |
平成23年 |
民国連携よるコンテナ苗の実証試験と普及 |
浄法寺森林官 福田 達胤 |
平成24年度 最優秀賞 |
|
10 |
平成24年 |
国民視点を意識した森林づくりの連携 | 流域管理調整官 小西 光次 技術専門官 松尾 亨 |
|
|
11 |
平成25年 |
天然更新を活用した牧草地の森林化について | 主任森林整備官 松尾 亨 | |
|
12 |
平成25年 |
ステレオ空中写真ペアを活用した、 |
小鳥谷森林官 北山 勝史 | |
|
13 |
平成25年 |
多雪寒冷地等におけるコンテナ苗の |
岩手北部森林管理署 三陸北部森林管理署 |
平成25年度 奨励賞 |
|
14 |
平成26年 |
「遊々の森」における環境保全活動と 森林学習の取り組み |
一般職員 塩谷 智也 新町森林官 下條 智人 森林技術指導官 小西 光次 |
平成26年度 優秀賞 |
|
15 |
平成27年 |
多雪寒冷地におけるコンテナ苗の成長及び下刈省略効果について |
地域技術官 市原 良浩 一般職員 谷地 真梨佳 |
平成27年度 奨励賞 |
1. カラマツ天然更新に関する一考察
技術専門官 松尾亨
林業に携わって来た方でもあまり聞き慣れないカラマツの天然更新を日常の業務の中からの疑問や発見から調査、開発してみました。
岩手県ではカラマツの造林面積が約12万3千haあり、この人工林を将来に引継ぐためにも低コストで確実な更新技術としての一考察となります。
2. 在来植物による緑化技術の開発
岩手北部森林管理署 工藤庸子
技術専門官 松尾亨
東野建設工業株式会社 羽柴 徳男
山地災害による崩壊地の緑化は治山事業として森林管理署の重要な仕事で、現在ではほとんどの崩壊現場においては緑化種子として外来種のトールフェスク・イタチハギなどを主に、行われています。
近年外来種の拡大繁殖による在来希少種の減少や衰退が心配されているなか、当署としては八幡平国立公園等の自然度の高い地域で周辺の植物生態系に配慮した工法が必要と考え、地元の在来植物による緑化技術を研究開発した内容をお知らせします。
3.特別発表 地域にとって有って良かったと思われる岩北署を目指して
岩手北部森林管理署長 春原 武志
国民視点に立った署の改革に取組んだ背景は、国有林地帯においても、地域と署の距離が広がっている一方、美しい森林づくりを進める上で、森林・林業の専門家集団である森林管理署に対する期待が高まっています。そのことを受け、山村地域の現状や課題について、実際に目で見、耳で聴き、解決策を現場で試みることができる森林管理署のメリットを活かし、地域のニーズを的確に把握し、地域にとって最善の選択肢を提案し、地域と協働で課題を解決することにより、「地域にとって有って良かったと思われる岩北署」の実現を目標にしました。
4. 発見!森林の秘密
岩手県八幡平市立田山小学校
5年担任教諭:菅原 由香里
5年児童:齊藤 豊:八幡 耀平:工藤 颯悠:安保 星奈:川又 美里:金澤 大都:吉田 大輔:田鎖 愛璃
僕達田山小の5年生は「森林(もり)」をテーマにした総合学習に取り組んでいます。周辺は90%が山林という環境に住んでいながら、初めて学ぶ「森林(もり)」には宝石箱をひっくり返したような新しい発見が次々とあります。
たくさん学びながら今回は「木の種類」、「木とわたしたちの生活」、「木の働き」の三つのテーマで調査してみました。
5.上外川学習教育林の整備について「妖精のすむ森をめざして」
浄法寺森林官 田口 暁史
新町森林官 木村 雄大
この取組みは、子ども農山漁村交流プロジェクトの受け入れモデル地区として葛巻町にある上外川国有林を舞台に、地元団体と意見交換しながら森林や環境等について、子どもたちが楽しく学べるようなフィールドを作り、妖精のすむ森をめざして整備し取り組みました。
|
|
|
|
|
特別発表 春原署長 |
子ども達と森林学習する工藤森林官 |
在来植物の緑化試験 |
|
|
|
|
|
カラマツの芽生え |
妖精のすむ森を木村・田口森林官 |
「国有林って何ですか?」佐藤次郎 |
6.「国有林って何ですか?」に応える、森林環境教育実施への一考察
販売係長 佐藤 次郎
森林教室等の環境教育活動を行っているなかで、環境教育活動は、国有林のPRに繋がっているのだろうか?参加している子どもたちは、普段森林、林業についてどのように考えているのだろうか?などの疑問や考えを持つようになりました。今後の環境教育活動の方向性を探ることを目的とてアンケート調査を実施した内容から国有林のあり方を探りました。
7.妖精の住む森を利用した森林環境教育リーダーの育成について
浄法寺森林官 田口 暁史
新町森林官 木村 雄大
リーダーとなるための知識や技術を学べるような研修があれば、「子ども農山漁村交流プロジェクト」の受入モデル地域でのプログラム開発や、森林環境教育の推進を図れるのではないかと思い課題を取り上げました。今後、森林環境教育の需要が見込まれるなかで中心となってインタープリティーションを行っていくリーダーを育成するためにはどうしたら良いのか、どんな問題点や課題があるのか、今後の理想のリーダー像について「子ども農山漁村交流プロジェクト」の2年計画のまとめとしての取り組みです。
8.天然更新を活用した牧草地の森林化について
技術専門官 松尾 亨
東北地方には、かつては森林であった箇所を地域振興策として、牧草地とし造成した箇所が多数あります。しかし、近年の畜産不振から返地を希望し再森林化の事業が増加しています。このような牧草地は、放牧、採草をやめてもオーチャードやチモシーなど外来牧草の根により森林化が難しく、植栽するにも大面積なため莫大な経費がかかるため、なかなか進んでいません。このような問題点を地掻きによる地表処理を行うことによって解消し、天然更新による森林化の道をさぐる試験を行った中間報告です。
天然更新を活用した牧草地の森林化について(PDF:580KB)
9.民国連携によるコンテナ苗の実証試験と普及
浄法寺森林官 福田 達胤
技術専門官 松尾 亨
育成係 渡辺 貞幸
岩手県林業技術センター主査専門研究員 木戸口 佐織
森林・林業再生プランにおいて、2020年の国産材自給率が50%の目標を掲げて進められているなか再造林費削減のためにコンテナ苗の普及が求められています。九州を始めとしたコンテナ苗の先進地と比較して普及が進んでいない多雪寒冷な気象条件下において、実証試験を岩手県内の民有林と国有林で実施し、問題点の改良に向け対策と改良を進めるため、岩手県林業技術センターと共同で行った試験と普及活動についての取り組みをまとめてみました。
民国連携によるコンテナ苗の実証と普及(PDF:3,676KB)
10.国民視点を意識した森林づくりの連携
流域管理調整官 小西 光次
技術専門官 松尾 亨
森林管理署が、「地域の声」を活かした事業や、地域ごとのテーマとともに取り込んで行く「協働」のなかから、地域に根ざした組織として国民視点に近づくことが出来ると考えられることから、明治期から続いてきた営林署の伝統と、平成になっての森林管理署が、国民の意識変革とともに今後さらに必要とされる組織としての事業の取り組みを調査し、変革の糸口とすべく岩手北部森林管理署の事業内容の検証を行った。
11.天然更新を活用した牧草地の森林化について
主任森林整備官 松尾 亨
東北地方の国有林には、かつては森林であったところを牧草地として造成し、市町村に貸付してきた採草地等がある。しかし、近年の畜産不振から返地を望んでいる箇所が増加傾向にあり、その森林化にあたっての経費が問題化している。天然更新にあたっての問題点を、地掻による地表処理により解消し森林化させることにより、従来の人工植栽より低コストで、郷土樹種による森づくりの施業方法の開発を目的に5年間調査した内容である。
天然更新を活用した牧草地の森林化について(PDF:910KB)
12.ステレオ空中写真ペアを活用した、効率的な林分材積把握システムの構築
小鳥谷森林官 北山 勝史
現在、広範囲の林分材積を把握するために、様々な方法が研究されています。空中から可視・不可視の光線あるいは、電波などで地表を走査するものが中心です。それらの方法の多くには、新たにコストを掛けて調査を行う必要があります。もし、既存の資料から広範囲に林分材積を把握することができれば、新たなコスト発生を軽減できるとともに、既存の資料の有効活用になると考え本研究に取り組みました。
ステレオ空中写真ペアを活用した、効率的な林分材積把握システムの構築(PDF:1,091KB)
13.多雪寒冷地等におけるコンテナ苗の改良と低コスト育林手法の開発
岩手北部森林管理署 主任森林整備官 松尾 亨
三陸北部森林管理署 首席森林官 河田 光美
主伐時の木材販売価格に対して、造林経費が高いため再造林の意欲が低下し、造林未済地の増加がみられている。多雪寒冷地な東北地方においてはコンテナ苗実証例が少ないため、コンテナ苗造林の課題解明が必要である。本研究は優良な苗と適正な育林手法の開発を目的に行った試験である。また、東日本大震災による海岸林の造成も急務で有り、海岸林の早期造成のため実証試験を行った内容である。
多雪寒冷地等におけるコンテナ苗の改良と低コスト育林手法の開発(PDF:996KB)
14.「遊々の森」における環境保全活動と森林学習の取り組み
一般職員 塩谷 智也
新町森林官 下條 智人
森林技術指導官 小西 光次
安比高原は、古くは地元住民による牛馬の放牧や製炭業が行われ良質なシバ草原とブナ二次林が成立していた。しかし、次第にその景観は失われていった。地域の財産である安比高原を次世代に残すべく、八幡平市と岩手北部森林管理署との間で、平成18年度に安比国有林約180ヘクタールが「あっぴ高原遊々の森」として協定された。以降8年間にわたり当署は市民と一体となり環境保全活動に取り組むと共に、遊々の森を活用した森林環境学習を継続して開催してきた。今回は平成26年度におけるこれらの活動状況について報告する。
「遊々の森」における環境保全活動と森林学習の取り組み(PDF:771KB)
15.多雪寒冷地におけるコンテナ苗の成長及び下刈省略効果について
地域技術官(森林育成担当)市原 良浩
一般職員(業務グループ) 谷地 真梨佳
利用期を迎えた人工林の循環的利用を図るために、伐採後の再造林の低コスト化が必須であり、その手段としてコンテナ苗植栽や下刈の省略が施業へ導入されつつある。当署では、実証例の少ない多雪寒冷地におけるコンテナ苗の成長特性や、下刈省略の効果を検証するため、平成23年度より試験地を設定し、局の技術開発課題としてデータ収集を行っている。本発表では、多雪寒冷地におけるコンテナ苗の成長及び、下刈省略効果についてこれまでに得られた調査結果を報告する。
多雪寒冷地におけるコンテナ苗の成長及び下刈省略効果について(PDF:875KB)
お問合せ先
岩手北部森林管理署担当者:森林技術指導官
ダイヤルイン:050-3160-5895
FAX:0195-72-2300