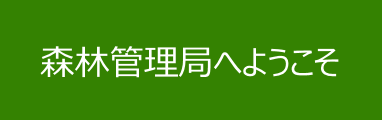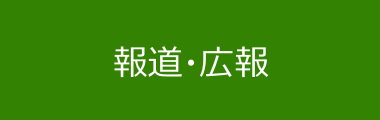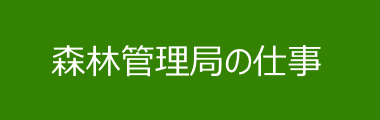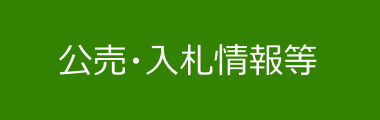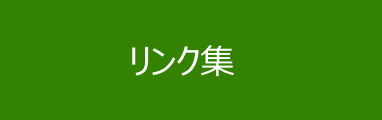三陸北部森林管理署
「署長が語る!」
平成30年9月
三陸北部森林管理署
署長 小野 義秀
はじめに
三陸北部森林管理署は、岩手県の沿岸北部に位置する宮古市、山田町、岩泉町(安家地区を除く)及び田野畑村の4市町村に所在する約6万7千haの国有林を管理経営しています。
さて、近年、日本各地で地震、局所的豪雨、火山噴火などが発生しておりますが、当署管内においても、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により特に沿岸部が甚大な被害に見舞われ、7年余りが経過する今なお防潮堤や道路の整備等をはじめ国・県・市町村等が一体となって復旧・復興に向けた取り組みが進められております。
しかし、平成28年8月には異例の経路をたどった台風10号による被害などもあり、計画とおりに進んでいないのが現状のようです。
今回の「署長が語る」では、当署管内における自然災害等による大きな被害について振り返ってみたいと思います。
大地震・大津波による災害
岩手県沿岸部等を襲った津波被害等を調べてみると、以下の災害があったようです。
(ア) 明治29年(1896年)6月15日三陸地震発生(明治地震)
・ この地震は、岩手県上閉伊郡釜石町(現釜石市)東方沖約200kmの三陸沖を震源として発生し、マグニチュード8.2~8.5の巨大地震(ただし、震度は最高で強(震度4~5)、宮古市は微-弱(震度1~2)程度)であり、地震に伴う遡上高(津波の高さ)が観測史上最高の海抜38.2mを記録し、甚大な被害を与えたものです。
・ 死者及び行方不明者合計:約2万2千人(うち岩手県:約1万8千人)。
(イ) 昭和8年(1933年)3月3日三陸地方大地震・大津波発生
・ この地震は、岩手県上閉伊郡釜石町(現釜石市)東方沖約200kmの三陸沖を震源として発生し、気象庁の推定によるとマグニチュード8.1の巨大地震ですが、明治地震同様に震度は宮古市等の震度5が最も強かったものの、地震に伴う津波の最高が海抜28.7mに及んだことにより甚大な被害を与えたものです。
・ この津波被害を教訓に岩手県下閉伊郡田老町(現宮古市)では昭和57年(1982年)までに海抜10m、総延長2433mの巨大な防潮堤が築かれ、そのうち昭和33年に完成した1期工事の防潮堤により、昭和35年発生・来襲したチリ地震津波の被害を最小限に食い止める事ができています。
また、このことにより、田老の巨大防潮堤は全世界に知れ渡ることとなりました。
・ 死者及び行方不明者合計:約3千人(うち岩手県約2千7百人)。
(ウ) 昭和35年(1960年)5月23日チリ地震による津波襲来
・ 昭和35年(1960年)5月23日(日本時間)南米・チリ中部沿岸に大地震が発生したことによって約22~23時間かけて太平洋を横断した津波が日本の太平洋沿岸を襲った(岩手沿岸部の野田湾や広田湾では6メートル以上に達した)ことにより被害を受けたものです。
岩手県内の死者及び行方不明者合計:約60人。
(エ) 平成23年(2011年)3月11日東日本大震災発生
・ この大震災は、記憶にまだ新しいところですが、宮城県牡鹿半島の東南東沖130kmを震源として発生し、マグニチュード9.0と発生時点では日本周辺における観測史上最大のもので、震源域も広大で岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmのおよそ10万km2に及びます。
・ 最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で、宮城・福島・茨城・栃木の4県36市町村と仙台市内の1区で震度6強を観測するとともに、場所によっては10m以上の高波や、最大の津波が海抜40.1mを記録するなど、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害を与えたものです。
・ 巨大津波による被害以外にも、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下、ダムの決壊などによって、北海道南岸から東北を経て東京湾を含む関東南部に至る広大な範囲で被害が発生し、各種インフラも寸断されました。
・ 被災後7年余りが経過した今でも避難生活を余儀なくされておられる方もおられ、各地域で復旧・復興に向けた取り組みが進められています。
・ 死者及び行方不明者合計(平成30年3月9日時点):約1万8千人(うち岩手県約5千8百人)
・ なお、この大震災では、当署庁舎、宿舎(宮古市磯鶏及び藤原宿舎)、森林事務所(宮古及び山田)の全壊、一部国有林において山林火災が発生するなどの被害を受けましたが、宿舎は平成25年に、庁舎は平成26年竣工にいたり、山林火災については平成29年までに跡地の植栽を終了したところです。
 |
 |
| 宮古市藤原地区平屋建て宿舎の被災状況 | 平成25年8月に完成した磯鶏宿舎 |
 |
 |
| 庁舎周辺の被災状況 | 平成26年3月に完成した庁舎(後方が磯鶏宿舎) |
○ 台風等による災害
東北地方は、台風の上陸が比較的少ないことから、甚大な災害をもたした事案も多くはありませんが、その中にあって、当署管内で台風により甚大な被害を受けた御山川上流部(アイオン沢)の関係をご紹介いたします。
なお、この地域における林野庁での復旧事業等詳細は、三陸北部森林管理署ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/sanrikuhokubu/)の「後世につたえるべき治山」をご覧ください。
(ア) 昭和23年9月16~17日台風21号
・ この台風は、昭和23年9月16日関東地方に上陸し、その後、三陸沖を東進し、期間降水量が宮古(岩手県宮古市)で249.3mmなど各地に洪水被害をもたらしており、国際名が「アイオン」であることから「アイオン台風」とも呼ばれています。
・ この台風により当署管内では、御山川や薬師川が増水や氾濫し、大崩壊地(約28ha)が発生したことにより、山津波が発生。(下流において誘発した荒廃地は約40ha)
・ さらに、その後、御山川にある土砂ダムが決壊したことから、閉伊川が氾濫して宮古市など下流一帯も大惨事に見舞われたものです。
・ 死者・行方不明者合計:約8百人(うち岩手県約7百人)。
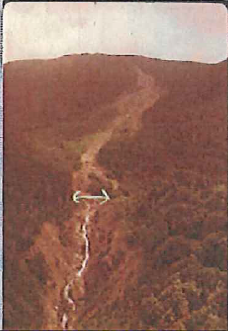 |
 |
| 昭和23年アイオン台風による御山川上流石合沢(アイオン沢)の被害遠景 | 昭和26年に完成したアイオン沢下流部御山川1号堰堤 |
(イ) 昭和55年5月21~22日台風3号
・ この台風は、日本に上陸していない模様で、国内に甚大な被害をもたらしてはいませんが、太平洋岸に沿うように北上しているため、地域によっては豪雨災害等が発生しています。今で言う「局所的豪雨」というところでしょうか。
・ この台風により当署管内では、御山川上流部等において5月21日夜半から22日朝方にかけて約60mmの豪雨があり、昭和23年アイオン台風で被害を受けた箇所等で再び林地の荒廃や土石の流出等被害が発生しています。
 |
 |
| 昭和55年台風3号による被害(アイオン台風被害復旧施工済み施設も被災) | 左の箇所の現在の状況 |
○ おわりに
近年では世界的にも火山噴火、地震及び台風等自然災害による未曾有の災害が発生しておりますが、規模の違いはあれ、同じエリアで自然災害等が発生しているケースもあります。
当署管内では、上述したほかにも高波や台風による被害などありますが、地域の安全・安心を確保するために治山施設等を整備して強靱な国土を醸成することや、森林が持つ公益的機能を十分に発揮させながら森林資源の循環利用を図って林業の成長産業化の実現に向けた取り組みを行っています。
お問合せ先
林野庁 東北森林管理局三陸北部森林管理署
〒027-0022 岩手県宮古市磯鶏石崎4番6号
TEL 0193-62-6448
FAX 0193-63-4872