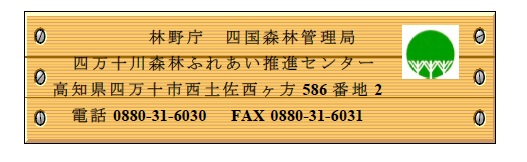![]()
ホーム > 森林管理局の概要 > 四万十川森林ふれあい推進センター > 活動内容 > 四万十の風音
平成27年1月発行
第44号
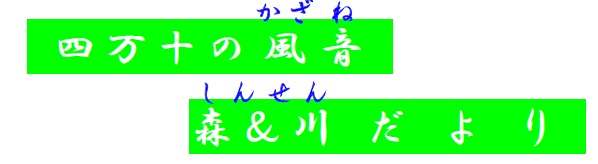
![]()
好天に恵まれた10月21日、滑床山頂(通称三本杭)において、関係機関及びボランティア団体等の関係者26名が参加し、第10回滑床山植生回復検討会を開催しました。
この滑床山頂周辺は、宇和島市、松野町、四万十市にまたがり、かつてはミヤコザサやオンツツジが群生していましたが、平成12年頃からニホンジカの食害により裸地化したことから、当検討会を平成18年6月に立ち上げて、ボランティア等の協力も頂いて山頂周辺の植生回復に取り組んでいます。
|
|
|
|
裸地化した山頂付近(平成8年10月) |
順調に植生が回復(平成26年10月) |
|
|
|
山頂付近の植生回復状況 |
今回で節目の10回目となる検討会では、平成19年3月にシカ防護ネットを設置して移植した「たるみ」及び「滑床山頂」のミヤコザサが順調に拡がり繁茂していることや、現地にある枯れ木などを活用した簡易な土留め措置の効果が現れ、リョウブやウリハダカエデなどの稚樹が順調に生育している状況などを確認しました。
当センターからは、「藤ヶ生越」周辺等のギャップに、シカ防護ネットを追加設置すること、「山頂」や「たるみ」及び「藤ヶ生越」のネット内は、植生が順調に回復しており、「これまでに色々な提言を頂いて、植生回復事業としての一定の成果が上がったことから、当検討会は今回で終了すること」を提案し了承されました。
また、滑床山頂周辺でニホンジカによる剥皮被害などを調査している森林総研から、ネット柵外では継続的に食害が発生しており、ニホンジカの生息密度は依然として高く、天然林内の自然植生に大きな影響を及ぼしていることなどが報告されました。
|
|
|
滑床山頂での検討会 |
出席者からは、シカ肉を食べて地元の資源を有効活用することが重要、ネット設置後のメンテナンスは、大変な業務であり、ボランティアによる協力も必要、相当数の捕獲実績があるが、増えているのが現状であり、色々な方法で個体数調整が必要等、引き続き関係者が連携してシカ対策に取り組む必要性などについての意見が出されました。
当センターとしては、新たなギャップが発生している中で、今後もネットを追加設置する考えであり、設置延長距離が益々増加する中で、ネット設置後のメンテナンスが大変な業務であることから、シカ防護ネットの保守点検等において、関係者やボランティア等の協力等も得ながら植生回復に取り組む考えです。
![]()
|
|
|
小筑紫小学校 |
当センターでは高知県と愛媛県の県境にある八面山から滑床山(通称:三本杭)に至る稜線のブナ林をフィールドにして、森林教室を行っています。
ブナやウリハダカエデ及びシロモジなどが紅葉する10月から11月、今年も高知県四万十市や宿毛市、愛媛県松野町の学校から約100名の児童らが訪れました。
登山道沿いの樹木やニホンジカの食害などを学習しながら、約50分で八面山山頂(1,165m)に到着しました。
山頂では、遠くに見える三本杭(1,266m)が、土佐藩と宇和島藩と吉田藩とがそれぞれの領地の境として杭を立てたことから「三本杭」と呼ばれるようになったことを話すと、驚いていました。
ブナ林へ移動してからは、森林の持つ様々な働きを学習した後、ネイチャーゲーム「カモフラージュ」と「フィールドビンゴ」を楽しみました。
○森林教室で八面山を訪れた学校
10月24日 高知県宿毛市立小筑紫小学校(5年生) 20名
〃 30日 〃 四万十市立利岡小学校(3~6年生) 26名
〃 31日 〃 四万十市立西土佐小学校(5年生) 24名
11月11日 愛媛県松野町立松野西小学校(4年生) 21名
|
|
|
|
|
松野西小学校 |
西土佐小学校 |
利岡小学校 |
![]()
|
|
|
銀世界の「堂ヶ森地蔵」 |
12月2日、黒潮町立三浦小学校の4~5年生の児童16名が堂ヶ森に登山しました。
例年、この時期には、小学生を対象にした登山を行っていませんが、本校の児童は今年度から「山の学習」を行っていることもあり、是非、今年中に登山をしたいとの依頼があり、今回の森林教室となりました。
今回の登山は、冬季の登山であることから、安全面を考慮し、1000mを越えない山で、学校からも比較的近い堂ヶ森(856.9m)を選定し、12月に入れば少し位の雪が降ることは、計算に入れていましたが、案の定、当日は、この冬一番の寒波到来により、一面が銀世界の中での登山となりました。
児童達は登山道沿いの雪景色を楽しみながら約1時間かけて堂ヶ森の頂上を目指しました。
途中の「四万十のヒノキ仙人」で休憩しながら、樹齢約250年の天然ヒノキの説明をし、実際に見た児童はその大きさに驚いていました。
堂ヶ森山頂のお堂では、「堂ヶ森」の名前の由来や「森林の大切な働き」について説明し、お堂周辺は多いところで5cm程も積雪があり、雪だるま等を作ったりして、楽しく遊びました。
その後下山し、バスの中での昼食。予定していたゲームは取り止めて、各児童からの「堂ヶ森」や「森林に関する」こと等について質問に対して答える方法にしました。
今回の登山で、暖かい地域で住んでいる児童達は、雪が積もることの経験が少ないので、銀世界の中での貴重な登山を体験し、自然の良さや大切さを十分感じてもらえたと考えてます。
|
|
|
|
「四万十ヒノキ仙人」の説明 |
「雪だるま」と記念撮影 |
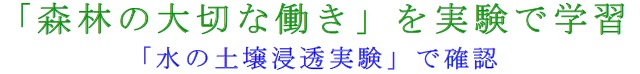
|
|
|
水の濁りの差を確認 |
10月10日、宿毛市立小筑紫小学校5年生20名を対象に「森林の働き」の学習を目的に「水の土壌浸透実験」を行いました。
森林の大切な働きである「水を蓄える働き」と「山崩れを防ぐ働き」について、「森林のある山」と「森林のない山」の治山模型を作り、ジョウロで雨を降らせて森林の大切な働きを学習しました。
「森林のある山」では、樹木や枯葉を通って出てくる水は透明になってビーカーに溜まっていくのに対し、木も枯葉もない土がむき出しの「森林のない山」からは濁った水がいつまでも溢れるように流れ続け、この違いを見た子どもたちは、「すごい!」と目を丸くして、2つのビーカーを見比べていました。
また、「森林のある山」は、木や落ち葉があって地面を直接雨で叩かれることはなく、森林土壌はスポンジのように雨を吸い込むのでなかなか土砂は崩れませんが、「森林のない山」では、雨が地面を叩いて地表を流れ、流出した土壌が斜面や山裾に置いた家の模型を倒していきます。
この実験後、児童からは「木が有る無しで水の色が全然違うことで、森林の力は凄い」などの感想があり、森林の「水を蓄える働き」や「土砂流出を防止する働き」を十分理解してくれたようでした。
![]()
○2校で木工クラフト教室
10月9日は、愛媛県松野町立松野西小学校で4年生21名、12月10日には、宿毛市立小筑紫小学校で5年生20名を対象に、木工クラフト教室をそれぞれ行いました。
両校とも木工クラフトに入る前に、「木材の特徴」と題して、「木は軽くて丈夫なこと、加工しやすいこと、湿度や温度を調整すること」等により、「木はその特徴を生かして、いろいろな生活用品に使われていること。」などをパワーポイントによる学習や木の重さの比較実験も行いました。
その後、松野西小学校ではミズメやヤマザクラの等の小枝を鋸やナイフを使い加工して、自分の想像力を生かし、世界で一つだけの作品を作製しました。
小さい枝は自分たちで切ることができましたが、太い枝を切る場合等は、当センターの職員や先生の手助けを得て、好みの大きさに切り揃えていました。殆どのこどもが休憩時間も忘れる程、夢中になって約二時間の作品製作に取り組みました。
子どもたちは、完成した作品を見せ合う等して、とても満足そうな表情でした。
また、小筑紫小学校では、職員から電動糸鋸の安全な使い方や注意点を習った後、作製に取り掛かりました。 児童達は、四班に分かれてクリスマスのドアノブ作りを行い、当センターの職員や先生の手助けを得て、板の円形部分を電動糸鋸を使い切断しました。
その後、紙やすりや色とりどりのポスカ及び木工ボンドを使用し、殆どの児童が休憩時間も忘れる程、夢中になって約2時間30分の作品作製に取り組みました。児童達は、完成した作品を見せ合う等して、とても満足そうな表情でした。
後日、小学校から送られきた児童の感想文には、「リグナムバイタ(世界一重たい木)は、とても重たくてびっくりしました。」「ドアノブ作り、最初は難しかったけど、楽しく作れて、以外に綺麗にできました。」「ドアノブ作りの準備、大変だったと思うけど、ありがとうございました。自宅に飾ります。」等の感想があり、森林や木材への理解の一助になれたと職員一同喜んでいます。
|
|
|
|
松野西小学校 |
小筑紫小学校 |
![]()

11月7日、愛媛県松野町立松野西小学校の四年生21名を対象に、今年度5回目の森林教室(炭焼き体験)を行いました。
始めに、スライドを使い炭の種類や利用法を説明し、白炭と黒炭の堅さの実験をしました。ノコギリを使用した炭の切断では、黒炭は簡単に切れるの対して、白炭は堅くて時間をかけないとなかなか切れず、黒炭との堅さの違いに驚いていました。また、白炭を木の棒でたたいて、「チンチン」と鉄琴のような綺麗な音色を楽しみました。
続いて、炭焼き体験。児童達は、職員から手順や注意点を聞き、ブリキ缶の中に、もみ殻とマツボックリやドングリ、折り紙で折った鶴など自分達で作った物を詰めて、ドラム缶のたき火の中へ並べました。
そして、アルミホイルに包んだサツマイモが炭になるかの実験もしました。たき火に入れて、約30分たった頃、ブリキ缶から出る煙の色が透明になる一方で、児童達はアルミホイルの中身が気になる様子でした。
どちらもたき火の中から取り出し、ブリキ缶が冷めるのを待つ間にアルミホイルを開けると、サツマイモは皮等の表面だけが黒く焦げて、残念ながら炭になりませんでしたが、焼き芋となり、みんなで美味しく食べました。
焼き芋を食べ終わる頃に、冷えた缶を開けると、折り鶴やドングリ、マツボックリなどはちゃんと炭になっていました。
![]()
○四万十うまいもの商店街
 11月9日、地元の四万十市西土佐江川崎で西土佐地域の秋の味覚を集めた「第三回四万十うまいもの商店街」が開催されました。当センターの木工体験コーナーを出店し大盛況となりました。
11月9日、地元の四万十市西土佐江川崎で西土佐地域の秋の味覚を集めた「第三回四万十うまいもの商店街」が開催されました。当センターの木工体験コーナーを出店し大盛況となりました。
このイベントは、「西土佐ふるさと市組合」の主催で、同地域に「道の駅」が開業する2015年を前に、西土佐を中心とした四万十川流域の地域グルメをPRしようするイベントで今回で3回目の出店です。
当日は、朝から生憎の雨模様の天気となり、テントに溜まった雨を再三除けるのに苦労しましたが、昼前頃からは小雨となり、地元産品等を利用した飲食販売や各種催し物が予定どおり行われ、人々の笑い声や歓声が各会場から絶えず聞こえていました。
当センターの木工体験コーナーのクマのストラップ等は、小学生の仲良しグループや親子連れ等が沢山訪れ「かわいい」と大人気でした。
天候には恵まれませんでしたが、地域との結びつきを深めるとともに、木の温もりを伝えられた秋の一日となりました。
○黒尊むらまつり
 11月15日、四万十市西土佐黒尊の黒尊親水公園で「黒尊むらまつり」が開催され、天気も良く、多くの方が黒尊渓谷の紅葉と流域の料理を堪能しました。
11月15日、四万十市西土佐黒尊の黒尊親水公園で「黒尊むらまつり」が開催され、天気も良く、多くの方が黒尊渓谷の紅葉と流域の料理を堪能しました。
このイベントは、黒尊川流域の住民グループ「しまんと黒尊むら」と「四万十くろそん会議」の主催で、同会議の構成員である当センターは「作って遊ぼう」コーナーと「八面山山登り」を担当しました。
当センターの「作って遊ぼう」コーナーでは、沢山の来場者で賑わい、サクラやミズメ等の小枝を使用したクマのストラップ作りを体験し、「八面山山登り」では、絶好の登山日和となり、参加された12名が八面山やブナ林などの自然や森林浴を楽しみました。
このコーナー周辺には、今年5月に新たに国民の祝日として平成28年から8月11日が「山の日」に制定されたことから、四国森林管理局が作成した「山の日制定記念」をPRする「のぼり旗」を建てて、来訪者に広く知ってもらいました。また、四国の森林等をフィールドとして、四国の森作り活動に積極的に取り組んでいる団体を表彰する「四国山の日賞」に選ばれた六団体を紹介するパネル展示も行いました。
メイン会場では、地元奥屋内の「お菊の滝」の言い伝えにまつわる「播州皿屋敷伝説」の紙芝居上演や、「黒尊むら市」には、地元の食材を使った炊き込みご飯、山菜おこわ、猪汁、鮎の塩焼きなどの地域の料理が沢山並び、来訪された方は流域の料理を食べたり、「神殿橋」周辺等の紅葉を見て、黒尊渓谷の自然を満喫されたようです。

滑床山及び黒尊山周辺におけるニホンジカの食害は依然として深刻な状況にあり、当センターでは、地元の猟友会に委託し、黒尊山と目黒山の国有林において囲いワナによるシカの捕獲を実施しています。
今年度は7月から12月までの半年間に、黒尊山9頭(雄4・雌5)、目黒山3頭(雄2・雌1)の12頭(雄6・雌6)捕獲しました。