![]()
ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 津軽森林管理署 > わぃはぁ通信 > 岩手県におけるコンテナ苗の状況現地視察の実施
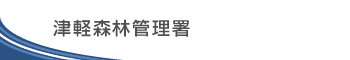
津軽森林管理署では、今年度よりコンテナ苗の普及促進を図るべく、今秋に現地検討会を開催する予定としておりますが、まずはコンテナ苗の現状把握が必要と考え、現在積極的に推進している岩手県のコンテナ苗の普及状況を視察し、コンテナ苗の知識を習得するため、現地視察を企画したところ、青森県、地元森林組合からも賛同をいただき、6月17日(火曜日)に実施いたしました。
当日は好天に恵まれ、青森県、弘前地方森林組合、地元林業事業体から8名、当署より6名、総勢14名が参加し、平成24年度に植え付けを行った岩手北部森林管理署管内のコンテナ苗試験地の視察、今年度コンテナ苗の植え付けを行っている箇所で植栽の実技、岩手県花巻市の横田樹苗でのコンテナ苗作りの現状視察などを行い、青森県におけるコンテナ苗の普及促進に向けて、関係者が一体となり推進していくこと、また、今後は、津軽流域林業活性化センターが主体となり、民国連携の取り組みに発展させていく必要性を認識して終了いたしました。
概要について次のとおりお知らせします。
現在、 国有林民有林の森林の状況を見ると、戦後に植林され伐期に達した造林地が多くなっています、そのような状況の中で、地球温暖化防止対策の森林吸収源の今後の課題として、森林の高齢級化による吸収量の低下があり、森林の若返り(再造林)を図ることにより、吸収能力を最大限に活かすことを推進することとしております。
森林の若返り(再造林)は伐期に達した森林を伐採し、植林を行い、再び森林にしていくことであり、今後、植え付けなどの更新作業を伴う施業が増加することが確実となっており、低コストでの造林作業の確立が急務になっています。
近年、コンテナ苗については、低コスト造林に有効な手段として全国的に普及が進んでいるところですが、青森県内でのコンテナ苗については、一部の種苗事業者が東北地方(岩手県、宮城県など)の説明会に出席しているものの、初期投資費用がかかるなどの理由から、ほぼ普及しておらず、コンテナ苗を植林したくても青森県内にはコンテナ苗がない状況となっていること、また、コンテナ苗は育苗を始めてから最低2年以上必要となることから、早急に国、県、市町村、樹苗事業体、造林事業体がコンテナ苗について理解を深め、導入に向かい協働で推進してく必要がある。
はじめに、岩手北部森林管理署管内に設定されたコンテナ苗試験地において、実際に普通苗とコンテナ苗が植栽後の成長の違い、また、植栽密度の違いにより下刈りに必要なコストの削減ができるのか、を試験しているプロットを見学しました。
|
|
試験地の概要 場所:岩手県八幡平市御月山国有林444林班る1小班 面積:2.90ヘクタール 内訳 1.20ヘクタール(スギコンテナ苗3600本 (3000本/ヘクタール)) 1.70ヘクタール(カラマツコンテナ苗4300本 (2500本/ヘクタール)) 植栽年:平成24年5月 (植栽後2年経過) 試験の目的:コンテナ苗と普通苗の比較による基礎調査、植栽密度の違いと下刈り軽減調査
|
下刈り軽減調査試験地では、下刈り実施プロットも下刈り実施前だったため植栽木が良く見えない状態だったので、植栽密度の違いについては良く確認できませんでしたが、1年目に下刈りを実施した箇所、しなかった箇所ではこんなに灌木などの生長が違うものかと驚きました。
植栽木への影響については、現在調査中ということで、特に比較できる状況ではありませんでした。

見学の様子
コンテナ苗と普通苗の比較による基礎調査地では、普通苗と比べてコンテナ苗の生長が早いように感じられましたが、どちらの苗も青森県に比べて生長が早く、参加者からは「こんなに生長が早いと雪による被害はないのか」といった質問がでました。また、見学したプロット内のコンテナ苗の生長が早く幹に多少の曲がりが多いように感じられたのか「この曲がりは雪の影響か、材質に影響はないのか」との質問もあり、岩手北部署では他にも試験地があり、そこで生長量、形状などの試験を行っているが、これまでの調査では本調査地のような曲がりは見受けられない、その辺も今後調査していきたいとのことでした。

見学の様子


コンテナ苗 普通苗
岩手北部森林管理署では平成23年より岩手県、森林総合研究所など関係団体と共にコンテナ苗に関する様々な試験を行っており、寒冷地におけるコンテナ苗の導入に向けて積極的に取り組んでいます。それでもなお、今後も試験研究が必要とのことで、これから始める青森県でのコンテナ苗の植栽においてもやはり様々な課題が出てくるものと感じられました。
しかし、低コスト造林の確立にはコンテナ苗による造林が不可欠であり、当署においても今秋予定されている現地検討会で試験植栽を行い、その後の調査を行いながら課題を整理していくことにしています。
今年度、岩手北部森林管理署でコンテナ苗の植え付け箇所があるとのことから、是非植付けの体験をしたいとお願いしたところ、快く了解をいただき、参加者の皆さんも初めてとなるコンテナ苗の植え付けを体験しました。
|
|
植栽箇所の概要 場所:岩手県八幡平市赤川山国有林1493林班るよ小班 面積:0.71ヘクタール カラマツコンテナ苗1450本(2000本/ヘクタール) 植栽年:平成26年6月 実行主体:岩手県森林整備協同組合 |
はじめに、岩手北部森林管理署職員より現地の概要、コンテナ苗の植え付け方法が説明されましたが、参加者の多くは初めて聞く説明が多く、興味津々といった状況で、周りで行われている植付け作業の様子が非常に気になるようです。



概要説明状況 植付け器具の説明 植付け器具の使用方法説明
参加者の多くが初めて見るコンテナ苗、植え付け器具、コンテナ苗の運搬状況を見学し、普通苗の植え付けの時と全く違ったもので、実際にどのような植付け作業となるのか楽しみです。
 |
カラマツコンテナ苗 2年生 150cc
コンテナ苗の根鉢の規格は300ccと150ccの2種類ありますが、最近では梱包、運搬、作業性の良い150ccが主流となりつつあるようです。 今回は150ccを採用していました。 |
 |
植え付け器具(名称はわかりません)
向かって左が300cc用 右が150cc用(今回使用) ずっしりとした重さがあります。 市販されているものはなく、注文して作っていただくそうです。 先の尖った部分の太さの変化が2段階になっており、土に刺さりやすく工夫されているようです。
|
 |
コンテナ苗の梱包状況
根の部分をラップで巻いており、乾燥と根鉢部が崩れないようにしています。 1梱包15本としています。(カラマツ、150ccの場合) これで、普通苗を植え付けする際に必要な仮植の必要がなく、2~3日はそのままで大丈夫だとのことです。
購入方法は1週間ほど前に種苗業者に発注し、前日か当日到着するように調整をしているようです、これも近くに種苗業者さんがあればこそできることです、 |
 |
コンテナ苗の発送状況
梱包したコンテナ苗を写真のとおり段ボール箱に10束詰め、1箱100本として発送します。(今回は150ccのため若干多め) あくまでもカラマツの場合で、スギの場合を聞くのを忘れました。 |
 |
苗木袋は普通苗のものを使用していました。 この苗木袋に30本を入れて植付け作業を行うようです。 |
実際に作業を行っている岩手県森林整備協同組合の方より植付け方を指導していただきました。
 |
まずは植え付けする場所を決めます。 当日は2000本/ヘクタールなので、縦横約2.2メートルの間隔になります。 |
 |
植え付け場所が決まったら、枝条などを整理します。 |
 |
整理が終わったら、植え付け場所に器具を使って穴をあけます。 今回の場所は土が軟らかく、石なども少なかったためか、特に力も必要なく、思ったよりも簡単に開けられました。 |
 |
植え付け器具を土に刺したら器具を動かして入口を少しだけ広げると苗を入れやすくなるそうです。 ただし、広げすぎると根と土が密着しなくなり枯れる危険性が高まるのでほどほどするとのことです。
|
 |
植え付け穴が開いたら、苗木袋から苗木を取り出し植え付け穴に入れます。 普通苗と同様に苗木袋の横穴(取り出し口)から取りだしても乱暴にしない限り崩れることはないとのことで、コンテナ苗の根の部分がしっかりと絡まっていることがわかります。 |
 |
苗木を植え付け穴に入れたら、土と根が密着するように押し込み、周囲の土をかけます。 |
 |
両足を使いしっかりと踏み固めをします。 この作業が活着率に大きく影響します。 この辺は普通苗と同様です。 |
 |
最後に乾燥を防ぐため、はじめに寄せておいた枝条などで根元を覆い完成です。 |
岩手県森林整備共同組合の方から丁寧な指導を受け、いよいよ参加者による植え付け作業開始です。
初めて手にする、コンテナ苗、触って見ると根の部分が均等に絡まり合って、崩れないようになっているのにまず驚きました。いよいよ植え付け器具により植え付け穴を開け植え付けを開始しました。
今回植え付けした場所は平坦で石などが混じってない非常に植え付け易い場所だったこともあり、皆さん簡単に植え付けをしていました。
植え付けする際に注意しなければならないのは、苗の根部と植え付け穴を密着させることで、植え付け穴に入れたあと手で押し込む作業をしました。これまでに体験したことのない作業で何か不思議な感じでした。
植え付けた感想は、想像したとおり普通苗に比べて早くて簡単という意見が大半でしたが、これできちんと活着するのかと不安な声もありました。
あまりにも簡単だったためか、1人で5本6本と植える方もいました。
  |
穴開け作業です。 これが急傾斜地だったり、石の多い場所、笹の多い場所だったらどうなのかと想像しながら作業しました。 従来の唐鍬だったら石に当たってたいへんなんだろうな、笹の根を切りながら掘らなければならないのかなと思いました。 別の場所でも試して見たいと思いましした。 |
|
|
植え付け作業です。 これが一番不思議な感覚でした、穴の開いた土に苗を押し込むなんて想像できない植付けでした。 植え付け後はしっかりと押し込み、苗の根部と土を密着させることが大切です。 それにしても、コンテナ苗の根部が主根と側根がきれいに絡みあって形が崩れにくいようになっていることに感心しました。
|
  |
最後は根踏みです。 この作業は普通苗の場合と同じなので、皆さん慣れたものです。 この作業の善し悪しが活着率と今後の成長に関係していることを皆さん知っていますので、しっかりと丁寧に行っていました。 |
岩手北部森林管理署では、今回の植え付け箇所において生長量の調査を行うこととしており、一部普通苗も植え付けしておりましたので、普通苗とコンテナ苗の形状の違いを見比べることができました。
枝の張り方の違いがよくおわかりになると思います、今後の生長量がどうなるのか調査結果が楽しみです。


普通苗 コンテナ苗
コンテナ苗の植え付けは、想像したとおり早くて簡単でした。
しかし、当初は技術的に確立しておらず活着率が普通苗に劣っていたことも導入の遅れにつながったとも聞いています。
現在はそういうこともないようですが、これから導入となる青森県では、この植え付け技術を身につけるところから始めなくてはなりません。、今後は林業事業体などへの普及、技術指導が必要となってきますので、そのような環境を整えることも大切だと感じました。
また、コンテナ苗の購入についても、岩手県のように注文から納入までを細かく迅速にできる環境になく、苗木の運搬途中の乾燥や蒸れなどの問題をどのように解決できるかが大きな課題となりそうです。そのためにも早期に青森県内でのコンテナ苗の生産が必要であると感じました。
岩手県花巻市にある横田樹苗(種苗事業体)さんにお邪魔して、コンテナ苗の育苗についていろいろと指導していただきました。
横田樹苗の横田さんは非常に気さくな対応をしていただき、また、これまでの体験(失敗談)などをまとめた資料を用意していただき、わかりやすく熱心に貴重なお話をしていただきました。
コンテナ苗の生産については、育苗技術が確立されており、ビニールハウスの中で均一な品質のものが大量に生産できるものだと思い込んでいましたが、横田さんのお話を聞き、大きな勘違いであり、苗の生産が非常にたいへんで、コンテナ苗による低コスト造林を確立するためには一番苦労しそうな感じを受けました。
横田樹苗さんの概要、指導内容などについては次のとおりです。
|
|
横田樹苗 場所:岩手県花巻市石鳥谷町 コンテナ苗については平成22年より栽培を始める。 これまでコンテナ苗と普通苗を栽培していたが今年度よりコンテナ苗に一本化した。 栽培に使用しているのはマルチキャビティコンテナ及びMスターコンテナで容量は150ccと300ccを使用しているが、現在は150ccが 主体になっている。 樹種はスギカラマツアカマツ抵抗性クロマツ(海岸防災林用)広葉樹(ケヤキナラ)を栽培。 出荷先は国有林が主体。 今年度は年間3万本を目標に出荷している。 |
今回視察しました内容をポイントごとにまとめました。
|
ビニールハウス看板 ビニールハウス内部
マルチキャビティーコンテナ150cc マルチキャビティーコンテナ300cc
Mスターコンテナトレイ Mスターコンテナ150cc
栽培用ピートモス |
資材などについてビニールハウスは冬期間の作業(播種を冬期に行う場合)や資材置き場として利用。 マルチキャビティーコンテナ 150ccは 40個/1トレー 300ccは 24個/1トレー の2種類を使用。 Mスターコンテナは150cc及び300ccの2種類を使用。 資材については岩手県山林種苗共同組合又は岩手県森林組合連合会を通じて調達している。コンテナについては日本製ではなく外国製か? 栽培用土にはピートモスなどの用土のほか水分管理用として鹿沼土を使用。 |
|
Mスターへの直播き 発芽状況
露地での育苗(遮光) 冬期の播験
苗置き棚 冬越しの説明
マルチキャビティ露地置き Mスター露地置き
|
水分管理コンテナ苗の栽培には水切り(根腐れ防止)と灌水(乾燥防止)が重要。 棚にコンテナを置いて生育しているときも、水が多く、水抜きが不十分であると根腐れを起こしやすくなる。 ハウス内にコンテナを置くと乾燥するため、冬(雪)が終わればハウス外にコンテナを直置きをする。(コンテナから出た根が畑に定着しないように注意する。 水抜きのために根鉢の下に糸を付けてみたがあまり効果がなかった、また、出荷の際に手で取り外さなければならず逆効果となった。
冬越し栽培するうえで一番の難関は冬越しである。春先に雪腐れが発生しやすい。 降雪前や十分な積雪がない状態で-15℃を下回ると寒風害が発生しやすい。 越冬はハウス外で雪の下のコンテナを寝かせると春先の根腐れが発生しにくいが、春先すぐに起こさなければ苗木が寝た状態で立ち上がり幹が曲がるので融雪後すぐに起こす作業が必要となる。
栽培条件、注意点などコンテナ苗の栽培地には、水、電気の調達が容易で道路に近いところが良い。 コンテナに直接播種したところ乾燥により発芽しなかったため、トレーに播種しその後コンテナに移植する方法をとっている。 25℃以上になると発芽や生長が停止する、昨年は夏以降の高温のため多くの苗が生育不良になった。 播種して2年目には追肥をしないと生長が大幅に遅れる。 ヒバは150ccは向かない。300ccでないと根巻きが発生したり水分過多で根腐れを生じると思う。 培土についてはココピート、肥料、表土に鹿沼土(表面のみ、土性の調整のため)を使用、鶏糞や豚糞を混合するとカビが発生するので避ける。アルカリ性ではなく酸性傾向にした法が生育がよい。 雪腐れ病防止のためには越冬前に濃度が高めの除菌剤を使用する。 畑に直置きしたコンテナ苗について、根が畑に定着してしまうと根切りをしなければならず、根切りをすると根巻きがうまくいかなくなるため注意が必要。 |
 |
植付けの注意点コンテナ苗は植え付け時に植え付け穴とコンテナ苗の根(土塊部分)を密着させることが重要で、空隙があると活着しない。 植栽時期について 1.カラマツ:7月から8月中は避ける(葉が若いため) 2.マツ:6月中旬以降(春先を避ける) 3.広葉樹:コンテナ苗であれば時期を選ばない(但し、畑に置いてある時点で根がはたけに定着してしまうと活着率が低下する。) |
|
Mスターコンテナ取り外し
挿し穂による育苗 |
その他Mスターコンテナの利点 1.マルチキャビティーコンテナと異なり、苗を生育途中で動かせること。これにより苗間を生長に合わせて変更できるので蒸れを防止できる。 2.苗木のコンテナからの取り外しが容易(取り外し機など専用機器が不用) 低花粉スギのコンテナ苗は実生(種から)ではなく挿し穂が有効。 普通苗とコンテナ苗では育苗期間が1年程度短縮できる利点がある。 出荷量の1.5から2倍程度の栽培量であれば事業として成立するのではないか。 普通苗に比べコンテナ苗は資材などによりどうしても原価が高くなるが育苗期間が短いので小面積で育苗でき、作業も少なくてすむ。
横田樹苗さんの平成22年から24年までの貴重な育苗記録をいただきましたのでこちら(PDF:894KB)をご覧ください。 |
今回、育苗の現場を視察して、これまでコンテナ苗については、コスト計算や造林技術など、普通苗との比較する試験、研究が多くされておりますが、コンテナ苗の普及、拡大には安定したコンテナ苗の生産技術の確立が必要であり、そのためにもコンテナ苗の生産に関する試験、研究がもっと行われ、効率の良い低コスト苗が大量に生産できるようになればと思いました。
いくらコンテナ苗による造林を実施しようとしても、コンテナ苗がなければ植付けすることができません、そのための苗の生産に樹苗事業体の皆さんが非常に苦労されている状況であることを参加者全員が感じ取ったと思います。
コンテナ苗が安定的に供給ができるようにする育苗技術の確立こそが、コンテナ苗による低コスト造林の普及、拡大の一番の課題だという意識を持つとともに、育苗施設の初期投資への支援の必要性や、コンテナ苗利用拡大に向け民国連携した中期的な需給調整など、樹苗事業体の育成強化に取り組まなければならないと感じました。
今回のコンテナ苗の現地視察を実施するにあたり、横田樹苗様、岩手県森林整備共同組合様、岩手北部森林管理署、盛岡森林管理署の皆様の多大なるご協力を賜り、この場をお借りしまして感謝申し上げます。
津軽森林管理署では、今秋にコンテナ苗の現地検討会を行うこととしておりますが、この度、津軽流域管理活性化センターとの話し合いを行い、今後、この取り組みについては津軽流域管理活性化センターが主体となり、民国連携で取り組んでいくことを快諾していただきました。
今秋に行われるコンテナ苗現地検討会については次のとおり予定することになりましたので、関係各位のご協力をお願いします。
開催日:平成26年9月18日 木曜日
概要:1.コンテナ苗の勉強会(仮称)、内容はコンテナ苗についての基礎知識の説明とこれまでの研究成果等の発表と質疑応答
2.普通苗とコンテナ苗の植え付け体験(仮称)、当署で今後植栽を予定している箇所において、普通苗とコンテナ苗を実際に植え付けを行い、植え付け作業の違いを体験する。また、植え付けた箇所を試験地として生長量等の追跡調査を行い、来年以降に調査結果を検討していくこととしております。
詳細については、決まり次第お知らせします。
今後も津軽流域におけるコンテナ苗の普及状況をお知らせしてまいりたいと思います。