![]()
ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 津軽森林管理署 > わぃはぁ通信 > 当署管内の種苗事業体による岩手県の種苗事業体見学会について
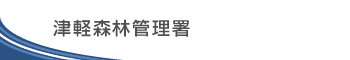
津軽森林管理署では、昨年度よりコンテナ苗の普及促進を図るべく、津軽流域林業活性化センター、青森県と共に現地検討会等を開催し、青森県におけるコンテナ苗の普及促進に向けた取組を実施しているところですが、この度、当署管内に所在する種沢種苗様より「是非、岩手県のコンテナ苗の生産事業体を見学し、勉強したい」との要請があり、6月17日に岩手県の横田樹苗様と吉田樹苗様を訪問し、コンテナ苗の育苗方法について勉強させていただきましたので、その様子をお知らせします。
現在、 国有林民有林の森林の状況を見ると、戦後に植林され伐期に達した造林地が多くなっています、そのような状況の中で、地球温暖化防止対策の森林吸収源の今後の課題として、森林の高齢級化による吸収量の低下があり、森林の若返り(再造林)を図ることにより、吸収能力を最大限に活かすことを推進することとしております。
また、山地災害の防止、森林資源の循環利用という観点からも、伐採した跡地には確実に苗木の植え付け、伐採前の森林に戻し、森林の持つ機能を維持していくことも大切です。
森林の若返り(再造林)は伐期に達した森林を伐採し、植林を行い、再び森林にしていくことですが、青森県での再造林の実績は過去3年で約3割程度に留まっているため、「青い森再造林推進プラン」を策定し今後、再造林放棄地の解消に向けた取組をしていくこととしています。
そのためには、森林所有者の再造林にかかる負担を軽くする必要があり、全国的に造林コストの削減のための様々な調査研究がされています。
近年、コンテナ苗については、低コスト造林に有効な手段として全国的に普及が進んでいるところですが、青森県内ではほぼ普及しておらず、本格的なコンテナ苗の生産事業体もないため、コンテナ苗を使用した低コスト造林を推進したくてもできない状況にあります。
青森県における再造林を推進するためには、早急に国、県、市町村、樹苗事業体、造林事業体がコンテナ苗について理解を深め、コンテナ苗導入に向け協働で推進し、低コスト造林を確立してく必要があります。
はじめに、岩手県花巻市にある横田樹苗(種苗事業体)さんにお邪魔して、コンテナ苗の育苗についていろいろと指導していただきました。
横田樹苗の横田さんはご自身でコンテナ苗を生産しているかたわら、コンテナ苗の品質向上と育苗技術の確立に向け日頃から研究しており、これまでの失敗談を含め貴重はお話しをしていただきました。
また、本格的なコンテナ苗の生産の前に、その地域の特徴を理解するため育苗実験をすることを進められ、実験にあたってはリスクの軽減のため、直接コンテナに播種するよりも、播種箱で発芽した幼苗をコンテナに移植したらどうかと提案され、移植方法についての指導もいただきました。
横田樹苗さんの概要、指導内容などについては次のとおりです。
|
|
これまでの体験談、失敗談、現在試していることまず、横田さんからこれまでコンテナ苗を育苗して様々な失敗をしたことを教えられ、その土地、その気候にあった育苗方法がある。 いろいろと試して見たが、自分ではこれで良いということはなく未だに試験しながら育苗している。 また、他の育苗事業体も様々な試みをしており、育苗技術は日々進化していると思う。 是非、早めにコンテナ苗を育苗してみて、自分なりの技術を見つけて欲しい、と激励を受けました。 種澤さんは、今回、息子さんと2人で参加しており、横田さんの研究心に感心していました。
|
横田さんの奥様より、播種箱で発芽したアカマツの幼苗をコンテナに移植する方法を指導していただきました。
本来、コンテナに直接播種し、発芽させるものですが、技術が確立していないと発芽率の低下を招くこと、また、発芽しなかったコンテナの穴に再度播種するか、移植しなければならないなどのリスクがあることから初めてコンテナ苗を育苗するには移植の方が確実ではないかとのことでした。
|
|
土詰め先ずはコンテナに培土を詰めていきます。 横田さんは培土の研究に特に熱心で独自の配合でココピート、鹿沼土、肥料、ミネラルなどを混ぜて使用しています。 今回使用したコンテナは、マルチキャビティコンテナの300cc 24穴で、横田さんは西日対策として白いペンキを塗装したものを使用していました。 このペンキについても実験途中だそうです。 |
 |
土の圧縮コンテナにある程度培土が入ったら、コンテナごと持ち上げ、下に落とし土を圧縮します。 前回お邪魔した際は、木の棒でコンテナ穴ひとつひとつをつつき圧縮していましたが、今回は中に詰める培土に水分を含ませ、培土の重さで圧縮していました、この方が作業性が良く、移植後の水分管理も効率的とのことでした。進化しています、作業も非常に楽です。 |
 |
土の圧縮後圧縮を3度ほど繰り返すと、かなり培土が沈みます。 横田さんは、結構強めにたたきつけるように圧縮すると良いと言っておりました。 |
 |
土詰め2圧縮により隙間があいたコンテナ穴に更に培土を詰めて平らにならします。 |
 |
移植穴開け作業特別に制作した道具により苗を移植する穴を開けます。 |
 |
移植作業アカマツの幼苗を金属の細長いへらのようなもので、根の先端が奧に入るように押し込み、培土で埋めていきます。 |
 |
苗を固定する金属のへらで埋めた苗を、まっすぐになるように手で押さえ固定します。 |
 |
完成これで24本完成です。 |
 |
種澤さんも移植作業を実習しました。 |
次に、岩手県気仙郡住田町の吉田樹苗(種苗事業体)にお邪魔して、コンテナ苗を生産するための施設などを中心に指導していただきました。
吉田樹苗さんは横田樹苗さんと共にコンテナ苗育苗技術を研究してきました。中でも大量生産に向けた設備の改良などに取り組まれており、自ら考えた、より使い易く、無駄のない機械や器具について説明をしていただきました。
今後、本格的なコンテナ苗の生産を行うためには、いかに作業効率を上げられるかを考えなければならない。そのためには作業する者が楽に作業できるかを考えることが必要である。
また、作業者が高齢化し後継者もなかなか見つからない中で作業者を確保するためには、作業内容を簡易にし、だれでも作業できるようにしなければならないと指導していただきました。
吉田樹苗さんでは今年度コンテナ苗だけで20万本の生産を目指しているとのことでした。
 |
用土攪拌機コンテナ苗を育てるには専用の用土を使用します。 用土は専用のものが市販されていますが、吉田さんはベースとなるココピートに肥料やミネラルなどを独自に配合したものを主に使用しています。 用土を作る際に大切なのは、十分に攪拌することということで攪拌機を使用します。 吉田さんは市販の攪拌機の高さを高くしたものを特注しています。 |
 |
専用作業台の制作吉田さんは攪拌機の高さを高くし、攪拌機の用土出口にコンテナが置けるような専用台を制作しています。 また、コンテナに土を詰めた後に、種を播種したり、移植するための移植穴を開けたりするための作業台も合わせて制作しています。 ご覧のとおり、楽な姿勢で作業を行うことができるので、作業者の体への負担が軽減され、作業効率も大幅にアップするそうです。 |
 |
スプリンクラーの設置状況説明コンテナ苗を生産するうえで最も大切なのは水の管理だそうで、事業体の多くが水の管理に苦労しているそうです。 特に大量に生産する場合には、灌水設備が必要となるとのことで、スプリンクラーの設置状況を説明していただきました。 |
 |
スプリンクラーの散水状況吉田さんは動力ポンプで汲み上げた水を、専用のホースで苗畑中に通水させ、スプリンクラーを設置しています。 スプリンクラーによる散水状況の写真ですが、分かりづらいと思いますので動画を掲載します。 散水状況の動画は こちら です。 注:動画の再生にはWindows Media Player が必要です。 |
 |
散水ノズルによる散水吉田さんはスプリンクラーによる散水のほか、散水ノズルによる散水を行っています。 雨が少なかった今年は大活躍だったそうです。 写真は消防でも使用されている散水ノズルで、無反動タイプだそうです。 苗畑中に通水させた専用のホースには、ところどころに散水ノズル用のバルブが設置されており、そこに散水ノズルを接続して散水します。 |
 |
散水ノズルによる散水状況散水ノズルによる散水状況の写真です。散水ノズルは広く、柔らかく、広範囲に散水することができます。 スプリンクラーで散水後に灌水状態を均一にするためにも使用しているそうです。 散水状況の動画は こちら です。 注:動画の再生にはWindows Media Player が必要です。 |
 |
コンテナ苗育苗状況コンテナ苗の育苗状況です。 手前はカラマツ、後方はスギで 150cc の苗です。 |
 |
アカマツの 300cc です。 今年度 20万本を目標にしているとのことでしたが、コンテナを置いている面積はそれほど広くなく、これで20万本あるのかな?と思うほどでした。 コンテナ苗は普通苗の三分の一程度の面積で育苗できるとのことで、納得しました。 |
今回、横田樹苗さん吉田樹苗さんにはお忙しいところ丁寧な説明やアドバイスをいただきありがとうございました。やはり、実際に育苗している方から話しを聞き、設備をみると、これまでの疑問や不安がなくなります。
種澤さんも今回の見学したことで、コンテナ苗の生産がより具体的に思えたのではないかと思います、何よりもご一緒した息子さんがコンテナ苗の生産をやってみたいとのことでしたので、今後、本格的な生産に向けて進んでいくのではと思いました。
後日、種澤さんから連絡がありまして、来年から少しのずつ始めたいと思っているが、今年のうちに試験してみたいというお話しがあり、150ccのコンテナを100枚分を試験的に育てることになりました。
津軽地方に少しずつでもコンテナ苗が広がっていっていただければたいへん嬉しいことです。
種澤さんの育苗実験については、別に掲載いたします。
![]()
津軽森林管理署
ダイヤルイン:0172-27-2800
FAX:0172-27-0733