![]()
ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 津軽森林管理署 > わぃはぁ通信 > 採材等合同現地検討会の開催について
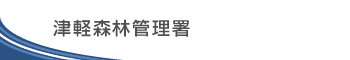
津軽森林管理署と津軽森林管理署金木支署では、森林整備事業及び製品生産事業で山林から切り出される木材をより有利に、また、より有効に活用されるように、管内の林業事業体等を対象に、「平成27年度採材等合同現地検討会」を開催しましたので、その様子をお知らせいたします。
当日は、好天にも恵まれ、実際に木材を切り出している事業体、木材から生産された丸太(製品)の品等区分を行う事業体、丸太を販売している事業体等から67名の参加で行われました。
・採材とは、山林から切り出された木材を日本農林規格に基づいて、長さ、太さ、品等(品質)を考慮により丸太(製品)にする作業です。
近年、地球温暖化防止対策として間伐などの森林整備事業が推進されていること、また、戦後植林したスギなどの人工林が主伐期を迎え、森林資源の有効活用及び伐採後の植林による森林の若返りと資源の循環を図る必要から山林から切り出される木材の量が増えつつあるが、切り出された木材をできるだけ有効に利用し、有利に販売することが、地球温暖化防止と林業の発展に結びつくことになるため、現在の丸太のニーズを踏まえた採材方法について、関係する事業体等の意思統一を図ることを目的とする。
平成27年6月26日(金曜日)
1.採材・巻立の説明
2.採材・巻立の検討
・巻立とは、生産された丸太売払いをするため、程度の量に積み上げる作業
まずは、開会式が行われ、主催者からの挨拶、事業地の説明が行われ、その後、実際に切り出された木材を各事業体ごとに採材を検討しました。
 |
まずは開会式です。 当日、進行役となりました、当署主任森林整備官より開会のことばがあり開会式がはじまりました。 |
 |
次に津軽森林管理署長より挨拶がありました。 地球温暖化防止対策として森林整備事業が推進されている昨今において、いかに効率的に丸太の生産を行うか、また、生産された丸太をいかに有効に活用されるかがたいへん重要です。 本日行います採材等現地検討会において、皆さんが共通の認識で丸太の生産を行い、生産された丸太が全て有効に利用されるように、しっかりと意見の交換をお願いしたい、と挨拶がありました。
|
 |
津軽森林管理署総括森林整備官より現地の説明、及び、平成26年度の材区分別生産量、長級別生産量、販売単価などの説明がありました。 また、採材寸法の考え方、日本農林規格の品等区分についても説明がありました。 |
 |
ここから参加した事業体が4班に分かれ、あらかじめ用意された全幹材に玉切るための目印をつけていきます。 曲がりや、節、腐れなどの欠点を考えながら、いかに効率的に採材するか検討をしています。
全幹材とは、立木を伐倒した後で枝などを切り落とした状態の材です。 玉切りとは、全幹材を丸太に切る作業です。 |
 |
丸太の長さは規格で決まっているため、長さの決定は非常に重要で、値段にも反映されます。 |
 |
東北森林管理局青森事務所の職員を交えて、各班で検討した採材について、全体で検討していきます。 |
 |
全体で検討した中で、いろんな意見があり、なかなか結論が出ない場合は、実際に高性能林業機械のプロセッサーで採材して検証してみます。 |
 |
実際に採材された丸太を計測して、検討結果を検証し、意見の統一を図ります。 |
 |
意見集約後、青森県森林組合津軽木材流通センター所長より、津軽地域の木材流通の状況や動向について説明をいただきました。
|
 |
続いて、青森事務所上席技術指導官より、東北森林管理局管内の木材流通の状況やニーズを反映させた今後の採材について説明がありました。 |
 |
最後に、金木支署長より、地域のニーズを踏まえた採材による林業の活性化、林業の活性化による再造林の推進など、今後の課題を地域全体で解決していくように連携していきたい、と講評があり閉会となりました。 |
近年、林業を取り巻く情勢は、地球温暖化防止対策として森林整備事業の推進や木材利用促進法の施行など注目されてきているところです。
しかし、現実は木材価格は思うように上がらず、なかなか苦労をしているところです。
そこで、林業に伴う低コスト化を推進しつつ、木材を有効に利用していただくように、林業に携わる方々が連携をし林業の活性化を図る必要があります。
また、木材利用についての理解を深めていただくためにもっと宣伝を行い、木材を身近な存在にしなければならないと考えております。
今後の活動にご理解とご協力をお願いします。
![]()
津軽森林管理署
ダイヤルイン:0172-27-2800
FAX:0172-27-0733