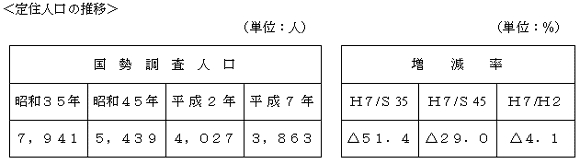| 区 分 : 都市住民と山村の交流 |
| タイトル : 「熊野古道」を観光資源とした自然と歴史を生かした町づくり |
| 都道府県名: 和歌山県 |
市町村名: 中辺路町 |
1 地域の概要
中辺路町は、東西に21㎞南北に12㎞の広域な町で、紀伊半島の中央部に位置し、総面積は県下4番目の211.95平方㎞で、その約93%が森林で占められている。
東は本宮町、西は田辺市、南は大塔村、北は龍神村に隣接しています。町域の大部分は山地となっており、町では昔から林業が盛んで、その他シイタケの栽培も行っています。また、農業は主に富田川と日置川沿いの平坦部を中心に、稲作などのほか紀州梅、シキミの栽培も行っている。
交通網は、基幹道路である国道311号線、県道龍神中辺路線が全線改良され、さらに国道371号線、県道平瀬上三栖線等の改良整備が進みつつある。
人口は、昭和31年の町誕生当時は、8,213人であったが、高度経済成長期において、都会へ流出して過疎化が進展し、平成2年には4,027人にまで減少し、現在は人口3,710人(平成12年国調)となっている。 |
2 事業(取組)の背景と経緯
(1)事業(取組)の背景
本町は、その名が昔の熊野三山への参詣道として栄えた熊野古道「中辺路街道」に由来するため、数多くの歴史的文化遺産に恵まれています。町では、これらの遺産を観光行政の軸に位置づけた。
(2)事業(取組)の経緯
恵まれた自然環境や森林資源、そして歴史的文化遺産「熊野古道」を町のシンボルとして全面に押し出し、町観光客増加による経済効果を求めるため、平成2年から「熊野古道絵巻行列」を毎年実施している。 |
3 事業(取組)の概要
古くから、山岳信仰の中心であった熊野、「蟻の熊野詣で」といわれるほど、貴族から庶民まで広い階層の人々が行き交い、十二世紀末、法王や上皇が大勢の貴族を従えて、熊野霊山を目指したこの熊野古道において、昔の風情を再現し、多くの人々が中辺路町を訪れ、古道の良さを知っていただくため、平成2年から平安衣装に身をつつみ古道を歩く「熊野古道絵巻行列」を開催している。県内外を問わず参加者を募集し、現在では、東京、大阪、兵庫など県外からさまざまな世代の参加者があり、毎年大変な賑わいを見せている。
また、町では平成5年頃から「熊野古道」の維持、復元、改修などの整備に本格的に取り組んできた。
例えば主な事業では、平成5年度から現在に至るまで毎年「熊野古道」沿いの看板や案内板の新設や修繕、周辺の刈りあらけや間伐などの森林施業を行った。平成8年度から平成9年度にかけて「熊野古道」沿いの高原地区にある「高野熊野神社」の修繕事業、平成11年度では、日本名水百選の1つ「野中の清水」の周辺整備、野中地区の「秀衡桜」の保護育成事業、平成12年度には、近露地区の「近露王子碑」周辺の整備など年々整備を進めてきた。
一方、現在町内には「いちいがしの会」という、環境を守るボランティアグループが発足しており、「熊野古道」周辺の手入れや「ナラ」「カシ」などの自然林樹木の植栽など幅広い活動を自主的に展開している。
このように、今日に至るまで行政と民間が一体となって、熊野の森復元に向けた活発な取組みを行ってきている。
~毎年町外から申込みが殺到する古道絵巻行列~ |
4 事業(取組)の成果(結果)
中辺路町を訪れる観光客は32万人で、その内熊野古道来訪者は年間10万人と増加してきている。
この増加理由は、「熊野古道絵巻行列」をはじめ、かつて開催された「南紀熊野体験博」の効果によるものと考えられる。更に今後、世界遺産登録が実現すればさらに多くの方が熊野古道を訪れることになる。
このような状況の中で、地域住民の取り組みが強化され、地域活性化の高揚がみられる。
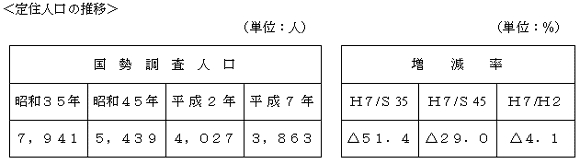
|
5 今後の課題
「熊野古道」が今後世界遺産登録されると、今まで以上に多くの来訪者が見込まれる。また、「熊野古道」が更に脚光を浴び全国的に有名な観光スポットとなるためには、「熊野古道」のルートとなっている近隣市町村との連携が重要であり、しかも、現在の「熊野古道」の姿を後世へと保存継承していくため、多くの人に「熊野古道」を知る機会となるイベントや、「熊野古道」周辺の整備に更に力を注ぐことで活性化を図っていく必要がある。 |