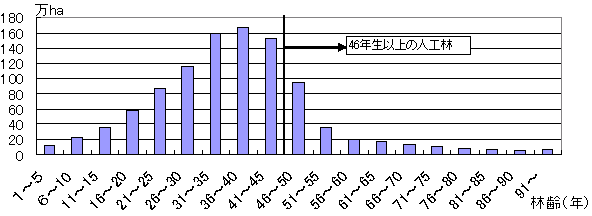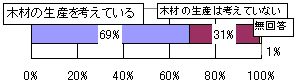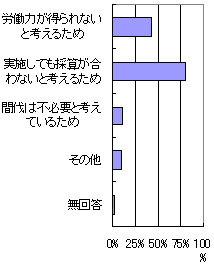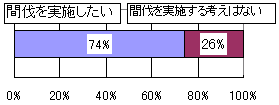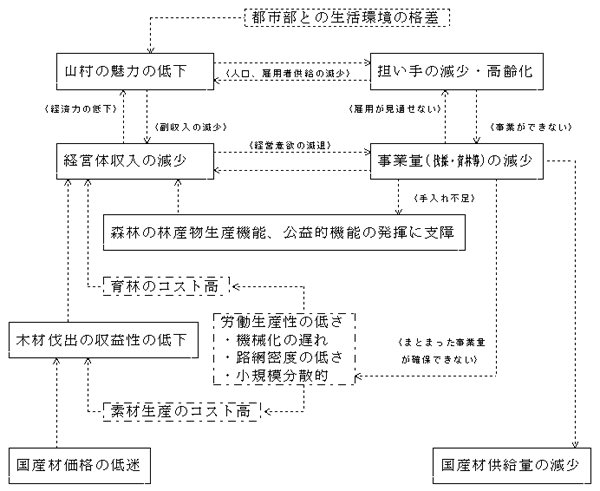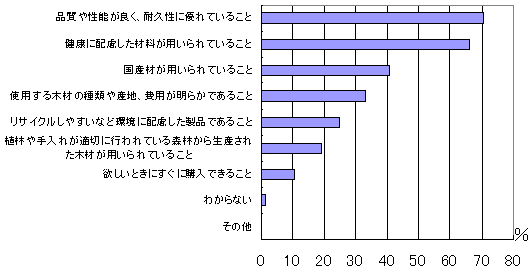Ⅰ 次世代へと森林を活かし続けるために |
|||
1 我が国の森林に求められているもの
|
|||
(我が国の森林の状況) |
|||
| ○ 平成16年は、台風、集中豪雨、地震等による山地災害や森林被害が多発したが、安全で安心できる豊かな暮らしを実現できるよう、災害に強い森林づくりを一層推進していく必要がある。また、このような森林の整備・保全を担う人たちが山村において安定的に就労し、定着することによって、将来にわたる森林づくりの展望も開ける。 ○ 国土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止等の森林のもつ多面的機能への国民の期待にこたえていくためには、いかに森林を良好な状態に保つかが大きな課題である。 ○ 森林の面積は、戦後昭和20年代半ばからほぼ変わっていないが、蓄積は人工林を中心に大幅に増加している。ha当たりの森林蓄積は現在161m3まで増加し、少なくともこの半世紀で我が国の森林資源は量的に最も充実した状況にある。 |
|||
|
|||
|
○ 人工林面積の約2割は一般的に伐採利用が可能となる林齢46年生以上であり、木材資源として利用段階に入りつつある。 ○ 森林の土砂の流出や崩壊を防ぐ働きは、適切に管理された人工林であれば天然林とほとんど変わらない。また、二酸化炭素吸収量の大きい針葉樹から主に構成されている人工林は、地球温暖化防止に果たす役割が大きいなど、人工林は適切に管理することで公益的機能の発揮が期待できる。 ○ 一方、我が国では、ササ、つる等の植物が繁茂しやすいことから、植栽から20年生程度までの集中的な手入れが必要である。また、降水量が台風時等に集中し、土壌が浸食されやすい環境にあることから、その後の適切な間伐が不可欠である。 ○ 人工林の手入れが十分でない状況が進めば、林産物生産はもとより、公益的機能の発揮にも支障をきたすおそれが増していくことになる。 |
|||
図Ⅰ−1 平成16年に日本に上陸した台風 |
|||
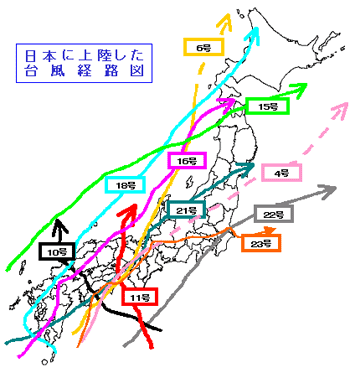 |
|||
図Ⅰ−2 我が国の森林面積及び蓄積の推移 |
|||
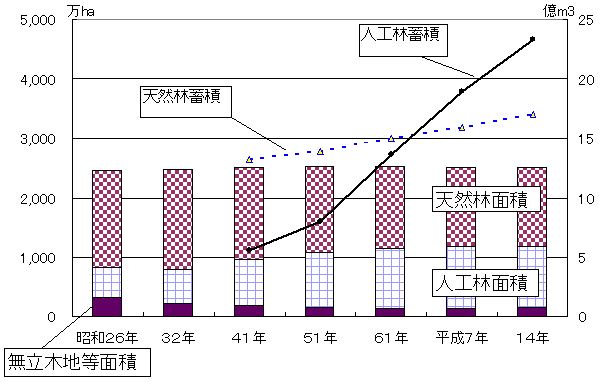 |
|||
| 資料:林野庁業務資料 | |||
表Ⅰ−1 昭和27年と平成14年の我が国の森林の比較 |