|
||
| ○ 平成16年の用材需要量は前年より増加し、国産材供給量については、2年連続で増加 した。特に、スギを中心に国産材針葉樹の合板への利用が増加した。また、我が国の丸 太輸出量は前年より増加した。 ○ 違法伐採対策として、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材 製品とする措置を導入することとした。 |
||
図Ⅳ-1 我が国の用材の木材供給量と自給率 |
||
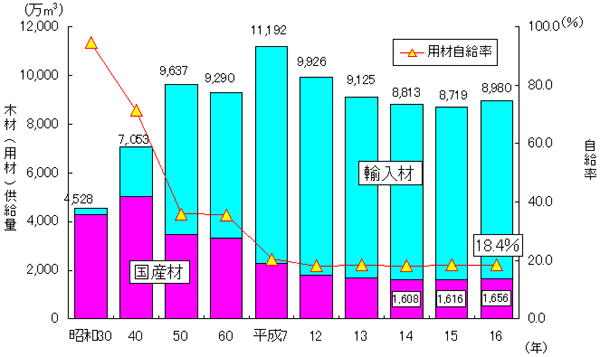 |
||
| 資料:林野庁「木材需給表」 | ||
図Ⅳ-2 国産材の合板用丸太供給量 |
||
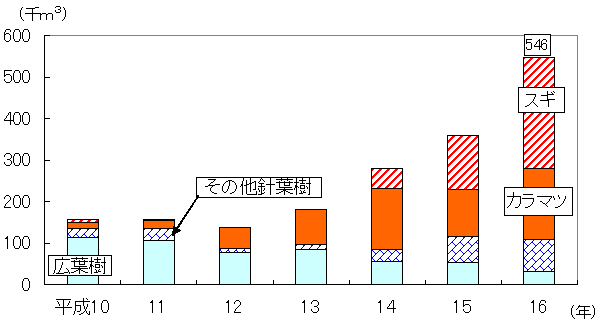 |
||
| 資料:農林水産省「木材需給報告書」 | ||
|
||
| ○ 平成16年の1製材工場当たりの平均従業員は5.9人で、4人以下が全体の6割を占め ている。また、出力規模が75kw未満の工場が7割を占め、小規模な工場が多い。 ○ 住宅建築においては、施工期間の短縮化や部材加工コストの低減化を図る観点等か ら、プレカット材の利用が増加している。柱材の樹種別シェアでは、欧州材を主体とする 集成材のシェアが急増しているほか、梁や桁等の横架材や土台においても集成材の シェアが増加している。 ○ 集成材への国産材利用は増加傾向にあり、スギ(国産材)とベイマツ(米材)を使った異 樹種集成材の生産が本格化するなど、国産材利用の拡大が期待されている。 ○ 国産材の需要を拡大するためには、品質・性能の確かな製品を低コストで安定的に供 給することが必要であり、川上と川下が一体となった消費者ニーズに即応できる供給体 制を整備することが重要である。 ○ 加えて、これまで利用が低位にあった曲がり材や短尺材についても、集成材や合板の 原料として供給する体制整備を推進していくことが重要である。 ○ 近年、印刷物、紙製缶飲料等日常生活において日頃手に触れるような身近な製品や、 道路のガードレール、新幹線車両の内装といった公共的な場所において、地域材利用 の広がりがみられるようになっている。 ○ 環境問題への関心が高まる中、林業・木材産業関係者は新たな需要に対応した製品の 供給を行うことが重要である。また、木材に対する正確な情報提供を行い、社会全体で 木材利用を進めていくことが重要である。 |
||
図Ⅳ-3 従業員数規模別及び出力階層別の 製材工場数の割合 |
||
|
||
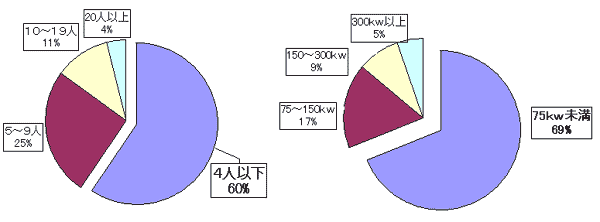 |
||
| 資料:農林水産省「製材基礎統計」(平成16年) | ||
| 注:製材工場出力数と素材消費量の関係の目安は、以下のとおり。 75~150kw:2千m3/年、150~300kw:5千m3/年、300kw以上:1万m3/年 |
||
| 図Ⅳ-4 木造軸組工法における柱材の樹種別使用割合 |
||
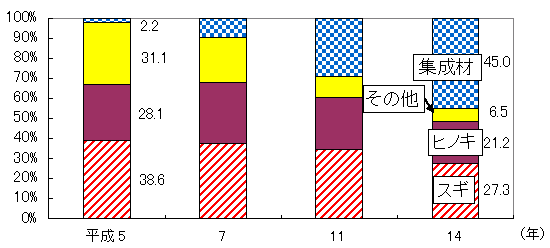 |
||
| 資料:住宅金融公庫「住宅・建築主要データ調査報告」 |