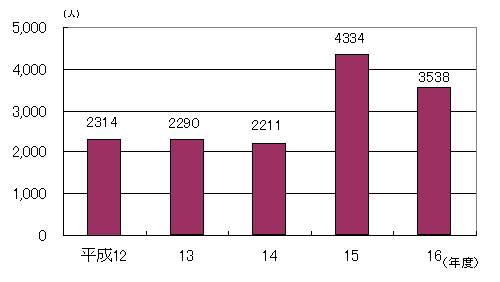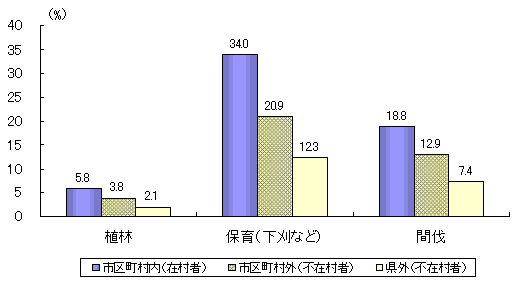Ⅲ 林業・山村の振興 |
1 林業経営をめぐる動き |
| ○ 平成16年のスギの立木価格は、昭和55年の5分の1、さらに平成17年には6分の1の水 準となっている。林業採算性の低下等により、森林所有者の施業意欲は減退している。 ○ 森林組合は、我が国の新植面積及び除・間伐面積の7割を実施する森林整備の中心的 な担い手となっている。森林所有者の不在村化や高齢化、世代交代が進むにつれ、自ら 施業や経営を行うことができない森林所有者が増加しており、森林組合による森林整備 への期待は大きくなっている。 ○ 平成17年7月に改正森林組合法が施行された。木材販売事業等の組合員以外の利用 制限の緩和、森林環境教育事業の追加等により、森林組合の機能と組織基盤の強化が 図られることが期待される。 ○ 間伐、再造林等森林整備の一層の推進には、成熟期を迎えた人工林資源を活用し、生 産・流通・加工のコストダウンと需要の確保によって森林所有者等の収益向上を実現す ることが課題である。 ○ このため、施業や経営の集約化、安定的な原木供給、需要者のニーズに応じた最適な 流通・加工体制の構築の取組を実施することで地域材利用を推進していくことが必要で ある。そして、これらの林業の再生を図る新しいシステムにより、林業のサイクルを適正 に循環させていくことが重要である。 ○ 生産性の向上によるコスト削減には、高性能林業機械と施業方法を組み合わせた作業 システムの導入や路網整備の推進等が必要である。 ○ また、森林の整備・保全に重要な効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育 成・確保が重要である。このため、新たな林業普及指導運営方針を策定し、普及指導 活動の方法の改善、実施体制の効率化、林業普及指導員の資質の向上等を推進して いる。 |
図Ⅲ-1 林業生産活動を取り巻く諸因子 |
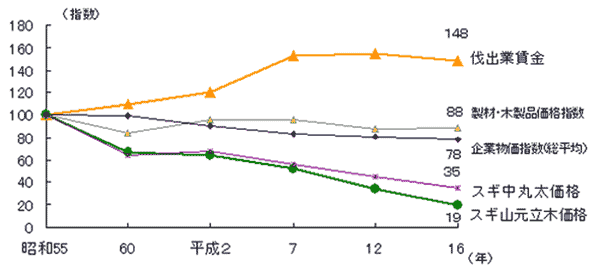 |
| 資料:日本銀行「企業物価指数」、厚生労働省「林業労働者職種別賃金調査」、(財)日本不動産 研究所「山林素地及び山元立木価格」、農林水産省「木材価格」 |
図Ⅲ-2 主伐を実施する意向とその理由 |
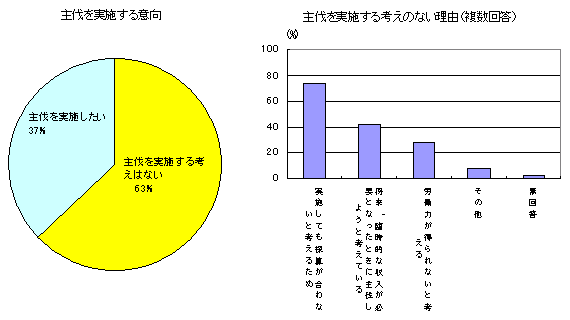 |
| 資料:農林水産省「林家の森林施業に関する意向調査」(平成16年7月調査) |
|
| ○ 林業就業者は減少傾向にあり、高齢化も進行していることから、長期的な就業が期待で きる若年層の確保と定着の促進が課題である。 ○ このような中、平成15年度から実施された「緑の雇用担い手育成対策事業」により新規 就業者は増加し、平成16年度には3,538人が新規に就業した。今後とも、林業就業に必 要な研修等を行い、林業への新規就業の確保を図ることが必要である。 |
|
| ○ 山村は、林業や木材産業をはじめ様々な産業活動を通じ、林産物や農産物の安定的な 供給に寄与している。 ○ しかし、山村では林業をはじめとした一次産業の衰退が、経済面や社会面に影響してい る。山村人口の減少、集落の小規模化、森林保有者の不在村化等、山村の活力の維持 だけでなく、森林の適正な管理への影響も懸念される。 ○ 特用林産物の生産は、山村における重要な産業の一つであり、今後も、原産地表示や 生産情報を消費者に提供していくことが重要である。 ○ 森林浴による、血圧低下やリラックス効果、免疫細胞の活性化が科学的に解明されると ともに、山村振興への寄与が期待される森林セラピーの取組が、産学官連携により展開 されている。 ○ 就業機会の確保や生活環境の整備とともに、都市と山村の共生・対流を進め、山村住 民だけでなく都市住民にとっても魅力ある地域づくりを進めることが重要である。 |
図Ⅲ-3 新規就業者の推移 |