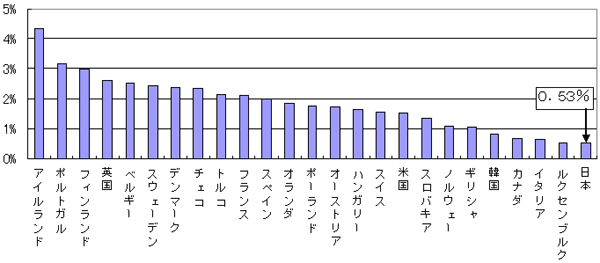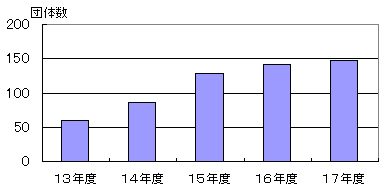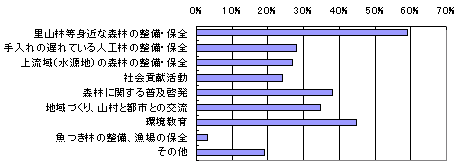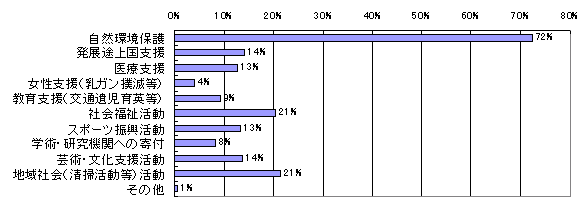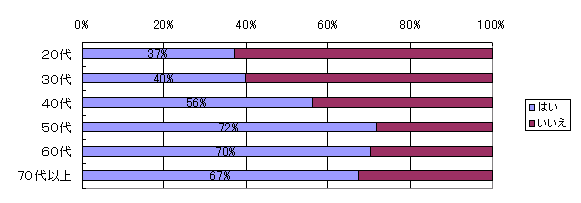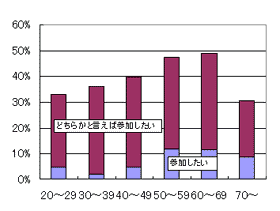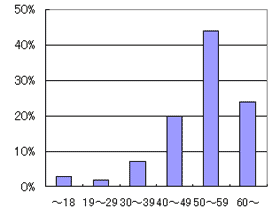Ⅰ 国民全体で支える森林 |
|||
1 急がれる森林の整備・保全
|
|||
(私たちの生活を守る森林) |
|||
| ○ 森林は、私たちの生活と深く結びつき、国民生活及び国民経済の安定に欠くことのでき ない「 緑の社会資本」である。森林の二酸化炭素吸収・貯蔵機能は、地球温暖化防止 の国際枠組である京都議定書でも重要性が認識されている。 ○ 京都議定書目標達成計画(平成17年4月閣議決定)においては、排出削減約束6%の うち、3.9%を国内の森林吸収量で確保することを目標としている。京都議定書の第1 約束期間開始が平成20年に迫っており、森林吸収源対策は差し迫った課題となってい る。 ○ 昨年から今年にかけて、台風等の自然災害が相次いでおり、森林の山地災害防止や 洪水緩和といった機能発揮に国民の期待は高い。 ○ 生物多様性保全や保健・レクリエーション機能等を含め、森林のもつ多面的機能を発揮 させていくためには、森林の整備・保全を更に進めていくことが必要である。 |
|||
|
|||
| ○ 木材価格の長期的な低迷と人件費をはじめとする経営コストの上昇の中で、間伐、保育 等の施業や伐採後の植林が行われない森林がみられるようになるなど、我が国の林業 生産活動は停滞してきている。 ○ 森林の整備・保全を進めていくためには、林業・木材産業関係者の努力、国や地方公共 団体の取組とともに個々の国民を含めた社会全体からの支援が必要である。 |
|||
表Ⅰ-1 京都議定書目標達成計画における温室効果ガスの 排出抑制・吸収の量の目標 |
|||
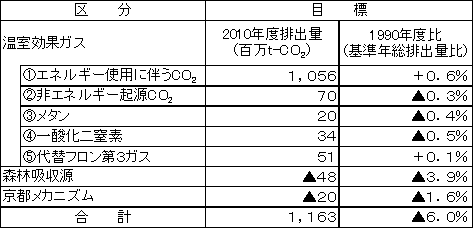 |
|||
| 資料:京都議定書目標達成計画(平成17年4月)をもとに作成。 | |||
| 注:京都議定書の第1約束期間における削減約束に相当する排出量と同期間における実際の温室 効果ガスの排出量(温室効果ガス吸収量控除後の排出量とする。)との差分については、京都 メカニズムを活用することを目標とする。(現時点各種対策の効果を踏まえた各ガスの排出量見 通しを踏まえれば、不足分は1.6%となる。) |
|||
図Ⅰ-1 森林のもつ多面的機能の貨幣評価 |
|||
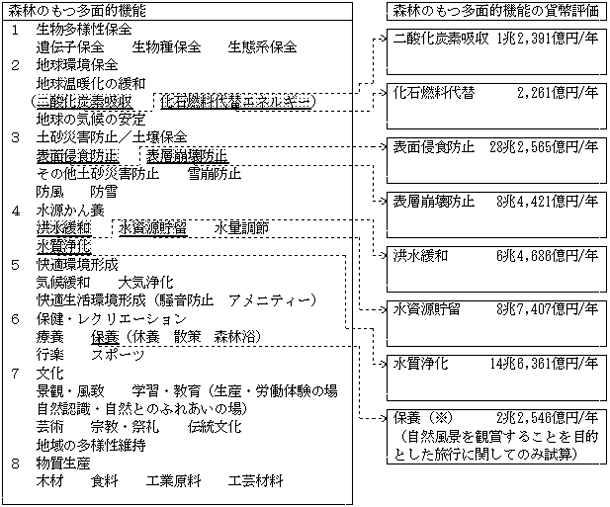 |
|||
| 資料:日本学術会議答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価につ いて」(平成13年11月)及び関連付属資料 |
|||
| 注:1)機能によって評価方法が異なっていること、また、評価されている機能が多面的機能全体のう ち一部の機能に過ぎないこと等から、合計額は記載していない。 2)※については、保養機能のごく一部を対象とした試算であることに留意する必要がある。 3)いずれの評価手法も、「森林がないと仮定した場合と現存する森林を比較する」等一定の仮定 の範囲においての数字であり、少なくともこの程度には見積もられるといった試算の範疇をで ない数字であるなど、その適用に当たっては細心の注意が必要である。 |